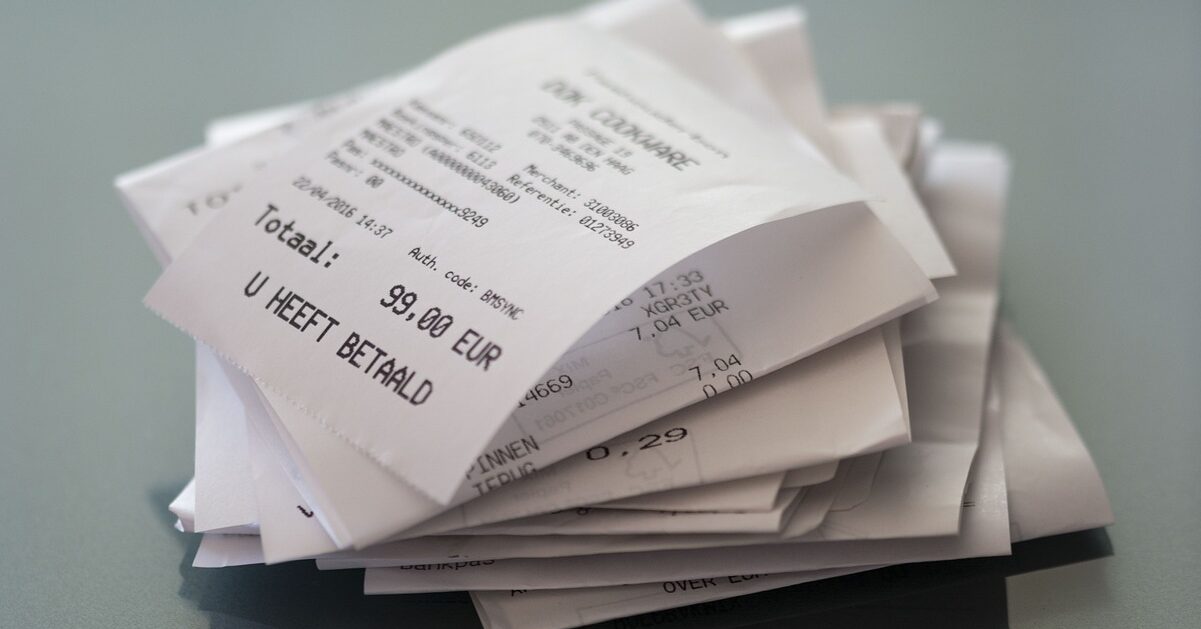インボイス制度開始後、買い手側の立場ですべきことって何だろう?
とりあえず、基本的なことを知りたい。
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
インボイスであるかどうかの確認
インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと。
まずは、受け取った請求書等の記載事項の確認です。
その請求書等が、インボイスであるかどうかの確認になります。

インボイスが無ければ、仕入税額控除が出来ないですからね、、、。
インボイスの確認
受け取った請求書等に、次の記載があるかどうかをチェックします。

電子インボイスのチェックも同様です。
簡易インボイスの確認
スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に対して販売等を行うもの)から受け取る請求書等については、簡易インボイスでもOKです。
飲食店などから受け取った請求書等については、次の記載があるかどうかをチェックします。

宛名の記載は無くても、大丈夫です。
その際、その請求書等に記載された登録番号が正しいものかどうか等についても、あわせて確認しておくようにしましょう。(インボイスでも簡易インボイスでも)
登録番号については、下記サイトでも確認可能です。
→インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)
「登録番号の確認って、毎回必要なんだろうか、、、?」については、下記ブログも参考にしてみてください。
インボイスの保存
確認ができれば、あとは、その保存です。
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス(簡易インボイス)を、7年間保存する必要があります。(厳密に言えば、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、、、。)
課税期間とは、基本的に個人事業主は暦年、法人は事業年度です。

電子インボイスの保存期間も、同様ですね。
受け取った請求書等の記載事項について確認したら、しっかりと保存することも忘れないようにしましょう。

もちろん、帳簿の保存も忘れずに、、、。
記載事項は、次のとおりです。
まとめ
今回は、『インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【基本編】』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。