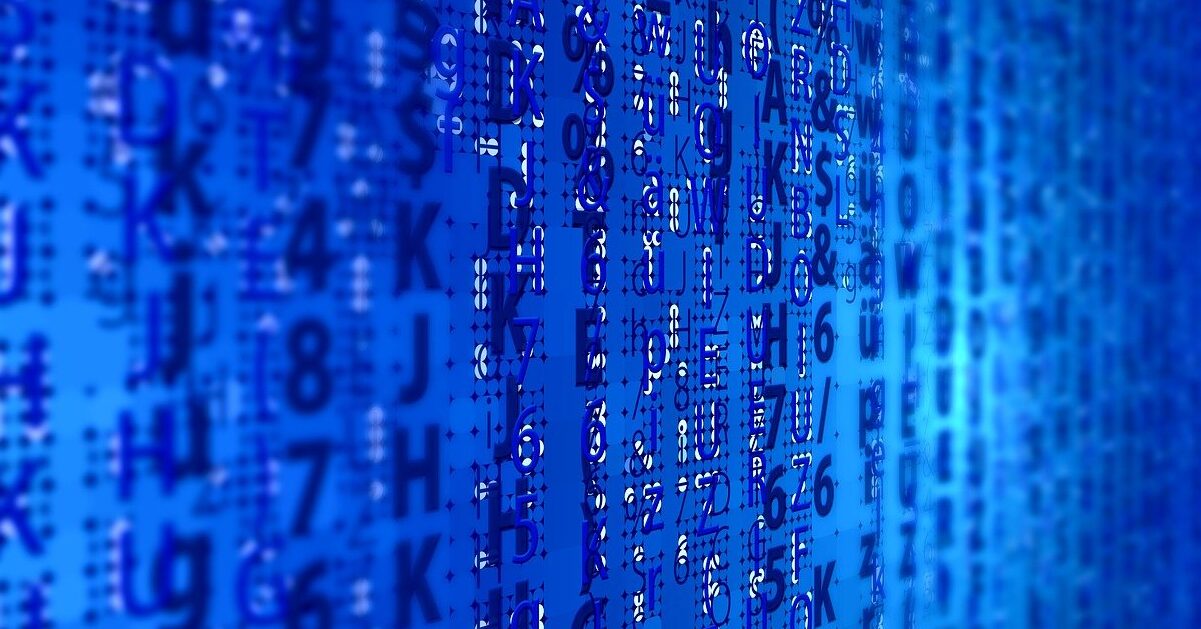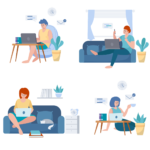
電子取引データ保存、、、
やっぱり対応が必要?
紙保存でもOKだったよね?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
令和6年1月1日以降、「電子取引データ保存」への対応が必須に!

電子取引データ保存とは、取引情報をデータで授受する取引(電子取引)についてデータ保存を義務づける制度です。令和4年1月1日以降の電子取引について適用されています。
取引情報とは、ざっくり言うと、注文書・契約書・送り状・領収書・請求書などのこと。
例えば、メールによる請求書等の送受信も電子取引に該当します。
なので、、、
請求書等をメールで受け取った場合には、「その請求書等をプリントアウトして保存するのではなく、そのデータ(PDF等)を保存しなければならない」ということです。
とは言っても、令和5年12月31日までは、事実上、紙保存でもOK。
「そのデータをプリントアウトして保存して、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればいいですよ」という宥恕措置があったからです。

準備が間に合わなかった
事業者に対する経過措置
ですね。
これまで通り、そのデータをプリントアウトして保存していた事業者の方も多かったのではないでしょうか。
ですが、、、この宥恕措置も令和5年12月31日で廃止に。
これにより令和6年1月1日以降は、いよいよ「電子取引データ保存」に対して、しっかりと対応していく必要性が出てきたのです。
Amazonからの領収書等のダウンロードなど、電子取引は案外身近にあります。
ほとんどすべての法人・個人事業主は、何かしらの対応が必要になりそうです。
電子取引の洗い出し
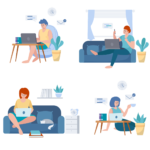
それで、、、
具体的にどう対応
したらいいの?
まず必要となってくるのが、「電子取引の洗い出し」です。
取引を整理し、電子取引に該当するものを把握します。
データでの授受ですので、受け取る場合のみではなく、送付する場合も含まれます。
その際、電子取引の件数なども確認しておきましょう。
今後の意思決定にも役立つと思います。
また、これを機会に、業務効率化のため何か見直せる部分がないか検討してみるのもいいですね。電子取引にできるものは電子取引にしていく、というのも一案です。
電子取引の保存要件に対応
次に、「電子取引の保存要件に対応」です。
電子取引データ保存は、電子取引の保存要件を満たした上でのデータ保存を義務づけています。
ただ単に、そのデータを保存すればいいというわけではないんです。
まずは、これらの要件をどのように満たしていくのかを検討し対応していく必要があります。

以下、具体的に解説します。
❶真実性の確保
「真実性の確保」とは、保存されたデータの改ざん防止のためのもの。
この要件を満たすためには、次のいずれかの措置が必要です。
この4つの中から、自社に合った方法を検討・選択します。
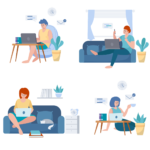
タイムスタンプ?
訂正削除システム?
少し難しいですよね。
おすすめなのは、4つ目の「事務処理規定の備付け」です。
タイムスタンプや訂正削除システムの導入費用等の追加コストも時間もかからず、対応可能です。
まずは「事務処理規定の備付け」を行い、必要に応じて、システム導入等の検討をしていくのもいいかと思います。
なお、国税庁が、事務処理規定のサンプルを公開しています。
自社向けに少しアレンジして作成することもできますので、ご参考に。
→国税庁/参考資料(各種規定等のサンプル)
❷可視性の確保
次に、「可視性の確保」ですね。
「可視性の確保」とは、保存されたデータを検索・表示するためのもの。
この要件を満たすためには、次の措置が必要です。
パソコン等の備付け
1つ目の「パソコン等の備付け」は、保存されたデータを速やかにディスプレイに表示したり、プリントアウトしたりするためのものです。
ディスプレイのサイズや台数に要件はありません。

なお、操作マニュアルは
オンラインマニュアルで
もOKです。
システム概要書の備付け
2つ目の「システム概要書の備付け」のシステム概要書とは、データ作成ソフトマニュアルなどのこと。
自社開発のプログラムを使用する場合のみ必要で、クラウド会計など他社製ソフトを使用する場合には不要ですので、ご安心を。
検索機能の確保
3つ目の「検索機能の確保」のためには、次の要件を満たす必要があります。
専用ソフトの使用も含めて、自社に合った方法を検討し対応していきましょう。
ちなみに、、、
一般の会計ソフトであれば、範囲指定検索や組合せ検索にも対応していますので、会計ソフトとの併用でも対応できそうですね。

あとは、ルール通り
にデータ保存をすれ
ば、OKです。
まとめ
今回は、『電子取引データ保存、対応が必要です!』について解説しました。
まずは、取引を整理し、電子取引を把握する。
そして、電子取引の保存要件をどのように満たしていくのかを検討し対応する。
あとは、そのルール通りにデータ保存をするという流れです。
なお、データの保存場所も決めておきましょう。
デスクトップのフォルダやクラウドストレージ上のフォルダなど、色々ありますね。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。