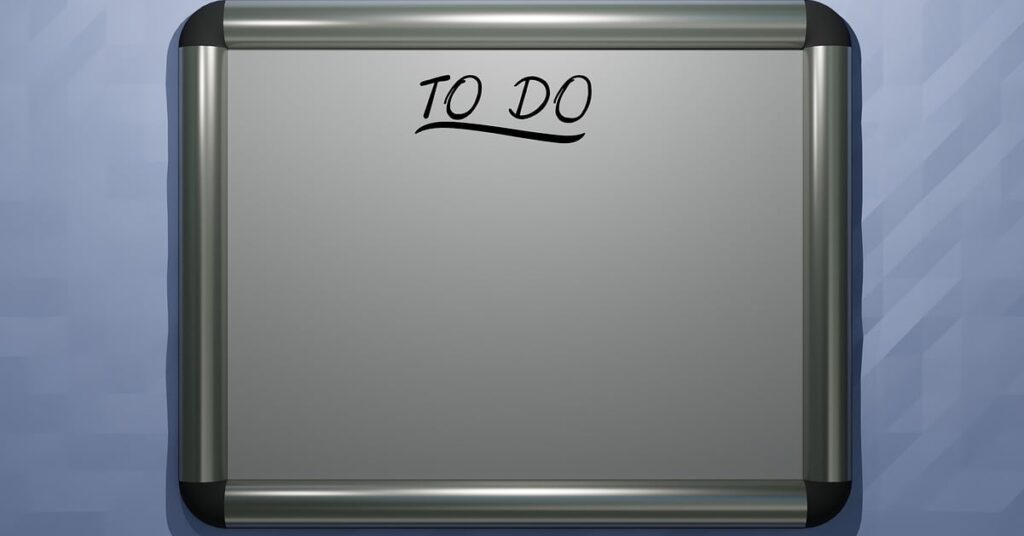少額特例?
少額かどうかって、、、
どうやって判定する?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
少額特例とは?
少額特例とは、一定規模以下の事業者が行う少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を認めるというものです。

令和5年度の税制改正事項
ですね。インボイスの保存
が不要ということです。
適用対象者は?
適用対象者は、
「基準期間における課税売上高が1億円以下」又は「特定期間における課税売上高が5千万円以下」の事業者です。
基準期間とは、個人事業主は前々年、法人は(通常)前々事業年度のこと。
特定期間とは、個人事業主は前年1月1日から6月30日までの期間、法人は(通常)前事業年度開始の日以後6月の期間のことです。
なお、特定期間における課税売上高については、(課税売上高に代えて)特定期間の給与等支払額の合計額で判定することはできませんので、ご注意を。

納税義務の判定とは異なる、
ということですね。
課税売上高とは、次のとおり。
また、「基準期間における課税売上高が1億円以下」“又は”「特定期間における課税売上高が5千万円以下」なので、いずれかに該当すればOK。
新たに設立した法人でその課税期間の基準期間がない場合は、特定期間の課税売上高が5千万円を超えたとしても、少額特例の適用対象者となります。
適用対象期間は?
適用対象期間は、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間。
制度開始後6年間の経過措置、ということです。
なお、事業年度単位や課税期間単位ではなく、令和11年9月30日までの課税仕入れが対象となりますので、その点ご注意を。
ちなみに、課税仕入れの相手先は、免税事業者でも消費者でもOKです。

もちろん、インボイス
発行事業者でもですね。
少額特例の「少額」の判定はどうする?
少額(税込1万円未満)かどうかは、1商品ごとの金額ではなく1回の取引の金額で判定します。
以下、具体例です。(インボイス制度Q&A 問112より)

❹の清掃業務については、
月単位の取引と考えます。
100,000円の取引ですね。
帳簿の記載事項
なお、帳簿の記載事項は次のとおりです。
、、、今までの記載事項と同じということですね。
「少額特例の適用がある旨」等の記載は必要ありませんので、ご安心を。

帳簿の保存(7年間)
も忘れずに。
まとめ
今回は、『少額特例とは?少額の判定単位についても解説!』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。