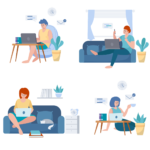
令和6年1月1日が課税期間
の中途の場合、電子取引の
対応はどうなるんだろう?
宥恕措置は、、、どうなる?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
【結論】「課税期間の中途」でも関係ありません。
今回は、【国税庁Q&A 問12】の質問より。
当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和5年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。
国税庁/電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問12より
令和5年度の税制改正は、令和6年1月1日以後の電子取引に適用されます。
なので、このように、ふと疑問に思っている方もいるのかもしれません。
結論は、次のとおりです。
令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、令和5年度の税制改正後の要件により保存しなければなりません。
国税庁/電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問12【回答】より
つまり、課税期間の途中であれ何であれ関係ない、、、ということです。
令和6年1月1日以後の電子取引については「改正後の要件」で保存し、令和5年12月31日までの電子取引については「改正前の要件」で保存するということです。

課税期間単位では
ないんですね。
宥恕措置を適用している場合は、どうなる?
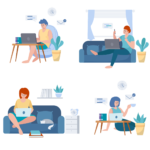
これまで「宥恕措置」を
適用して紙保存をしてい
たんだけど、、、?
令和5年12月31日までの電子取引については、「宥恕措置」を適用して保存している方も多いかと思います。
その場合は引き続き、(令和5年12月31日までの電子取引については)そのプリントアウトした書面を保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしておけばOKです。

保存期間が満了する
まで、ですね。
そのうえで、令和6年1月1日以後の電子取引については、令和5年度税制改正後の要件で保存しましょう。紙保存OKの「宥恕措置」は令和5年12月31日をもって廃止されますので、ご注意を。
なお、令和5年度税制改正を踏まえた対応(「検索要件の緩和」や「猶予措置」を踏まえた対応)については、下記ブログで解説しています。
ぜひ、参考にしてみてください。
まとめ
今回は、『【電子取引】令和6年1月1日が課税期間の中途の場合、どうなる?』について解説しました。ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。



